力強く生きることを教える羽根不動院
力強く生きることを教える羽根不動院
昭和57年7月号
羽根の南の山の中。雑木林に覆われ薄暗く、夏の木漏れ日が鹿の子模様を作る森の中。
弘法大師の一夜作りと伝えのある不動尊を祀り、安楽寺の奥の院と言われている羽根不動院。
石造五輪塔を中心に大小の石造や石灯籠が四、五十基、木陰に見つけることができる。
これらの銘は、天正年間(1575年前後)から始まり、正徳年間(1716年前後)のものが多い。羽根を中心に近郊の人びとの信仰を集め、その歴史の古いことがうかがわれる。毎月10日が命日で、2月は護摩会、8月には大般若会が行われ、多くの参拝者でにぎわう。
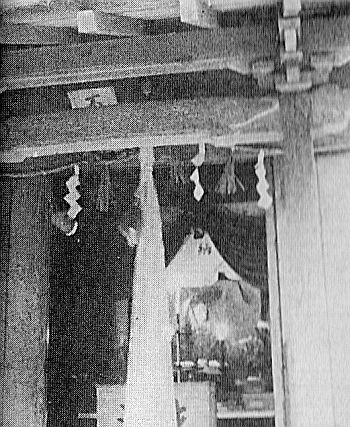
案内をいただいた川口忠一さんの話によると、大般若会に使われる大般若経は天保の頃、羽根の村民が五十両(現在の500万円程度)の資金を集め、京都で600軸の般若経を買い、16名の代表が、笠間峠越えで、持ち帰ったとのことである。これが羽根不動講のはじまりとのことである。経本は字寺の安楽寺に現在も納められている。
御堂深く岩に刻まれた50cmほどの不動明王像は、焔髪の頑につきさすようなするどい眼、牙をむき出して武器で威嚇する。その忿怒の形相はすさまじく、みつめる人々をふるえあがらせる。他の仏像には見られない御姿である。
堂の奥には不動尊の剣が光る
また、天正伊賀の乱の頃、田畑は荒され打ちひしがれた民衆が、この不動院で、戦の過ぎるのを祈ったのだという人もある。
昭和57年目次
19.元旦の初歩きコース尼ケ岳登山 昭和57年1月号
20.商売繁盛と福徳の神青山恵比寿 昭和57年2月号
21.近代的な装いを見せる矢持橋界隈 昭和57年3月号
22.老川の地に創建された伊賀東照宮 昭和57年4月号
23.水車の水も引いた宮の淵井堰 昭和57年6月号
24.力強く生きることを教える羽根不動院 昭和57年7月号
25.下川原の恩人前川の祐年(ゆうねん)さん 昭和57年9月号
26.流されたご神体高尾の神明宮 昭和57年10月号
27.昔ながらの神事を続ける阿保東部大当講 昭和57年11月号
28.伊賀と伊勢を結ぶ『しおないの道』 昭和57年12月号