奥山権現
奥山権現
昭和62年10月号
青山高原に鎮座する奥山権現は、正しくは奥山愛宕神社といい、火の神(火之迦具土神=ひのかぐつちのかみ)を祀る。県道伊賀青山線を勝地(通称よのみの辻)から分岐する勝地林道にそって約6kmのぼった所にある。この林道のスギ・ヒノキの美林はすばらしい。
創建の由来は明らかではないが、慶長13年(西暦1608年)藤堂高虎が伊予国(愛媛県)から伊賀へ転封にさいし、随従してきた家臣山内某が信仰していた権現さんを伊賀、伊勢の国境いに近い現社地の霊域にお祀りしたのに始まるという。
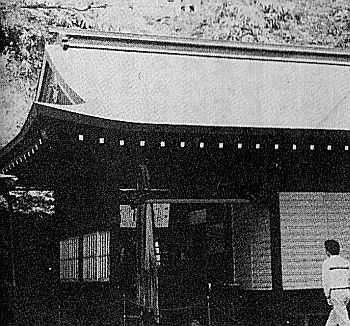
天明の初年(西暦1782年)諸国に眼病が流行した時、目の患者たちが平癒を祈願して霊験があってから名声は近畿一円に広がったという。勝地の村はずれにある一の鳥居の「是より五十一丁」に始まる丁石が、現在28基建っている。欠損ごとに補充したので、明治、大正、昭和さまざまである。残存のものでは明治7年の「奥山大権現是ヨリ三十三丁」が一番古い。近年地区の人等の努力で参詣道の80%が舗装され、車の通行も随分楽になった。
権現さんから、東海道自然歩道を1.2kmゆくと青山高原展望台である。また境内の社叢の「ブナの原生林」は、昭和48年県の天然記念物に指定され、渓流には珍しい「箱根サンショウウオ」が生息している。
戦時中、伊賀の各地から歩いて山越しに武運長久を祈った頃から早40余年の歳月が流れたが、奥山川の清い流れは昔も今も変わらない。
昭和62年目次
77.いまも残る老川如来への道 昭和62年1月号
78.青山のお大師さん 昭和62年2月号
79.江戸時代から伝わる諸木のドンド 昭和62年3月号
80.江戸時代初期の一里塚 千塚さん 昭和62年4月号
81.磨崖仏だった岩鼻(いわっぱな)地蔵 昭和62年5月号
82.瀧の権現さん 昭和62年6月号
83.社日(しゃにち)さん 昭和62年7月号
84.神宮崇敬の象徴参宮街道筋の石造常夜灯 昭和62年8月号
85.珍しい石造りの牛頭天王の社 昭和62年9月号
86.奥山権現 昭和62年10月号
87.羽柴砦 昭和62年11月号
88.町内で最も古い石塔 岡本家の十三重塔 昭和62年12月号