初代斎王の頓宮跡か照皇宮神明社(しょうこうぐうしんめいしゃ)
初代斎王の頓宮跡か照皇宮神明社(しょうこうぐうしんめいしゃ)
平成2年12月号
国道165号線の新羽根橋南詰めから分かれて、町道を東へ約100m戻った道路端に「奉灯照皇宮」と銘のある高さ3mの自然石の灯籠ある。これは対岸の前深瀬川(まえふかせがわ)と木津川の合流点近くに鎮座する「照皇宮神明社」の灯籠である。
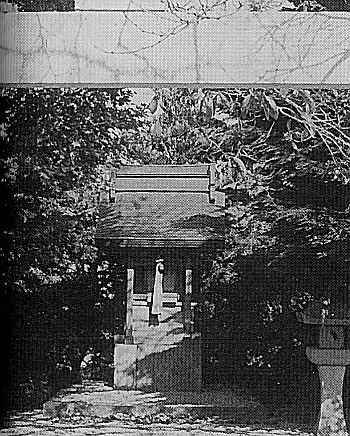
同社は、かつて将軍森という大木の茂る森の中に祭られていたが、明治40年(1907)大村神社に合祀(ごうし)された。戦後羽根下出の30余戸の方々が、社地跡に鎮守の神として再び祭ったもので、祭神は大日孁貴命(おおひるめのむちのみこと)(天照大神)である。
三国地志などにも記載されているように、第11代垂仁天王の皇女で、息速別命(いこはやわけのみこと)の姉にあたる倭姫命(やまとひめのみこと)が大和の笠縫邑(かさぬいのむら)に祭られていた天照大神から伝えられた御鏡(後の皇大神宮の御神体)を奉持して、その鎮座地をさがすため伊賀に来られ、8年間滞在されたとき、ここにも立ち寄られた仮宮の跡であり、したがって初代斎王の頓宮跡でもあるという、確証はないが神話的な伝承がある。
頓宮跡としては、阿保上代が有名であるが、長い間には、ここにも何度か頓宮が置かれたかもしれない。
今、境内には昔の巨木はないが、銅板瓦屋根の小じんまりとした社で、鳥居・灯籠・社名石柱・のぼり立てや、大きな参籠所も建って、立派な神社の形態を整え、毎年4月に大村神社の宮司さんを招いて、大祭を斎行している。
平成2年目次
113.伊賀・伊勢の境 布引峠の今昔 平成2年1月号
114.伊賀の中山 平成2年2月号
115.諸木のふれあい広場 平成2年3月号
116.指形の道標が示す川上の大円寺 平成2年4月号
117.江戸の文化を今に伝える伊賀名句集 平成2年5月号
118.伊勢路の天王はん 平成2年6月号
119.諸木氏城跡 平成2年7月号
120.県指定文化財「たわらや」の看板類 平成2年8月号
121.県指定天然記念物 奥山権現のブナ林 平成2年9月号
122.名張の沃野(よくや)をうるおす新田水路 平成2年10月号
123.弘法大師の三度栗 平成2年11月号
124.初代斎王の頓宮跡か照皇宮神明社(しょうこうぐうしんめいしゃ) 平成2年12月号