湯神楽の笹は水難除け水神まつり
湯神楽の笹は水難除け水神まつり
昭和56年8月号
7月・8月は夏まつりの季節、各地の社(やしろ)やお寺・地蔵さんでは、いろいろと趣向をこらした、まつりや会式(えしき)が催される。毎年8月4日の夜、阿保橋のたもとで行われる『水神まつり』は昔から阿保の夏まつりの第一号として親しまれてきた。
最近では、公民館まつり、農協納涼会、商工まつりなど、神仏不在、人間さま中心の夏まつりが年々盛大になり、こちらの方はいささか影が薄れた感じがする。しかし「水神さん」の愛称で呼ばれるこの夏まつりは、今も古風どおり水神碑の前に据えられた大釜で湯神楽(ゆかぐら)が炊かれ、その熱湯で清められた笹が参拝者に授与され、この笹は水難除けのお守りになるといわれている。附近の町並みには七夕が飾り付けれられ、造り物コンクールや映画会が催され、人出を見越した露店も賑やかに軒をならべて多くの人を集める。
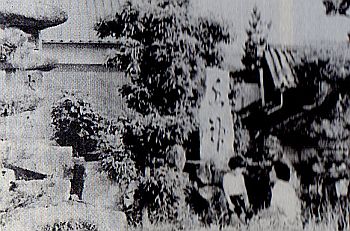
夏まつりとは、もともと、水の神、火の神など、人間生活に密着した大自然の恵みに感謝し、水難火難を防ぎ、家内安全を祈願するための祭りが主体である。神の心をなぐさめるため奉納する神楽や花火が人気を呼び、主客が転倒してしまっているようだが、その代表的なものが、阿保の水神さんであり、名張や上野の愛宕神社の火まつり(花火)である。
阿保橋の右岸に立つ水神碑
夏の夜を華やかに彩ってくれるこれらの夏まつりが、むし暑い夜の清涼剤となり、また風物詩として欠かせないものになっていることはいうまでもない。
昭和56年目次
7.伊勢参りの僧が再建した護国山天照寺 昭和56年1月号
8.阿保親王といわれる息速別名の墓 昭和56年2月号
9.寺と桜と滝とうたわれた名所の滝仙寺 昭和56年3月号
10.万葉の桜がしのばれる阿保山の桜 昭和56年4月号
11.小川内で発見された石器の原石 昭和56年5月号
12.奥鹿野で語りつがれた神穴伝説 昭和56年6月号
13.深瀬渓谷の隠れた名滝高尾観音瀑 昭和56年7月号
14.湯神楽の笹は水難除け水神まつり 昭和56年8月号
15.天正伊賀乱の緒戦地伊勢路掛田城 昭和56年9月号
16.青山最古の開拓地か羽根塚原遺跡 昭和56年10月号
17.秋まつりの伝統行事獅子舞い 昭和56年11月号
18.天狗の難所がトンネルに伊賀の中山 昭和56年12月号