老川の中世城館 若山氏城
老川の中世城館 若山氏城
平成8年8月号
足利将軍義満の全盛期で、金閣寺が建てられた応永年間(1400年頃)、老川の土豪だった若山七郎が、宇西谷の山上に城を築いた。若山氏城とよばれるこの城のことを、青山町史は『老川如来の北西300mの出張り山地の山頂にあり、三方切り込みは2段になっている。前方部はかきあげ土塁である……切り込み土塁の高い所は10mに達する壮大なものである。城内は32×20m』と書いている。
町内では、このような中世の城跡が50ほど確認されているが、若山氏城は築城時の遺構がよく保存され、貴重な文化財だと言われている。
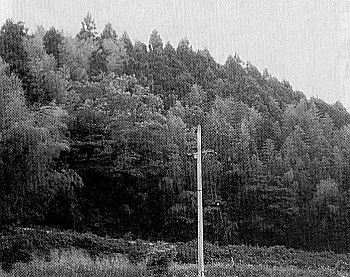
城といってもこの時代の城は、上野城や大阪城のように平地に高い石垣を築いた城ではない。山頂や山腹の一部を平坦に削り、周囲に土手を築き、内部に防護と住居を兼ねた館(やかた)を造ったもので、外側の土を採った跡を空堀にした構えになっている。
伊賀軍が全滅し、住居はいうに及ばず、神社仏閣のすべてが灰にされた、天正伊賀の乱(1581年)の時には、伊勢地(路)の掛田城や、柏尾の本田城などとともに、青山峠から攻め込んで来た織田軍の本隊に果敢な戦いを挑んだ城だったと思われる。
この城から少し下がったところに、古屋敷とか丹波屋敷と呼ばれる館跡もあり、丹波の国から来た若山氏が、最初に土着した所だという。その子孫は江戸時代藤堂藩の無足人となり、老川の庄屋にもなった。
平成8年目次
185.笛吹の伝説と千方(ちかた)の四鬼窟(よつおにいわや) 平成8年1月号
186.山中半右ヱ門 本陣跡碑 平成8年2月号
187.最も代表的な古墳 羽根・狐塚古墳群 平成8年3月号
188.ロマンただよう桜峠の春 平成8年4月号
189.奥鹿野の菩提寺 保徳山久昌寺 平成8年5月号
190.霧生の鉱山跡 平成8年6月号
191.小さな磨崖仏(まがいぶつ)阿保の子安地蔵さん 平成8年7月号
192.老川の中世城館 若山氏城 平成8年8月号
193.権現谷の双つ渕(ふたつぶち) 平成8年9月号
194.腰山の峯道(みねみち) 平成8年10月号
195.朱の欄干と金色の擬宝珠 大村橋 平成8年11月号
196.矢生(やお)中学校の上高尾分校 平成8年12月号