阿保宮道筋の「かんせい」地蔵と薬師堂
阿保宮道筋の「かんせい」地蔵と薬師堂
昭和61年4月号
阿保東部宮道筋の大村神社大鳥居から下約60mの北側に、二つの御堂があります。
その一つ、藤棚をくぐった奥にある御堂は、四角の石の正面に地蔵菩薩を彫刻してあり「寛正5年(1464)」の年記銘があって、室町時代前期の作です。これは五輪塔の一部の地輪で、塔として完全にそろっていれば、町文化財にも匹敵する、時代の古い仏様です。
昭和のはじめ、付近の方が畑を耕作中に土中から発見し、以前からおまつりしていた「石占(いしうら)(重軽石)」という石神様(五輪塔の水輪)とともに、御堂を建てて安置したものですが、願いがかなうときは軽く上がり、かなわないときは重くて上がらないそうです。
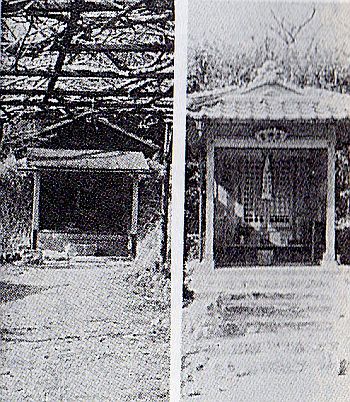
もう一つの、道端の高い所にあるのは薬師堂で、創始は判明しませんが、このほど信者の寄進によって立派に改築されました。
石に刻んだ薬師如来が御本尊で、足痛に霊験あらたかとされ、治癒したときは、大きな「わらじ」を奉納し、また妊婦や乳の出の悪い産婦は、米を供えて願をかけ、そのお下がりで「かゆ」をつくって食べるとよく出るようになるといわれ、お礼に綿を布で包んでつくった乳房を奉納します。
地元では、毎年8月26日に両方の会式を盛大に行い、催し物としての福引大会は有名です。
昭和61年目次
65.高原の守り神 古田の市杵島神社 昭和61年1月号
66.伊勢路善福寺と藤堂作兵衛奉納の観音様 昭和61年2月号
67.薬師さん 昭和61年3月号
68.阿保宮道筋の「かんせい」地蔵と薬師堂 昭和61年4月号
69.天満神社の“珍しい山の神々” 昭和61年5月号
70.正治権現(しょうじごんげん)さん 昭和61年6月号
71.伝説「千方の笛吹き石」 昭和61年7月号
72.信仰と散策の浄域十七明神社跡付近 昭和61年8月号
73.旧峠道に建つ高座子宝地蔵 昭和61年9月号
74.一本松の地蔵さん 昭和61年10月号
75.河川の神 弁天様 昭和61年11月号
76.幻の温泉郷も含むなつかしの阿保小唄 昭和61年12月号